農兵節と三島女郎衆
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 【お台場】 | |
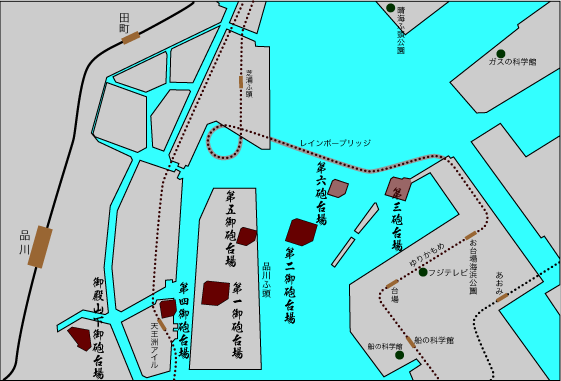 |
|
 |
 |
| 【お台場と大砲基台跡】 |  |
| 嘉永6年(1853年)、ペリー艦隊が来航して幕府に開国要求を迫る。これに脅威を感じた勘定奉行の川路聖謨らが動き、幕府は江戸の直接防衛のために海防の建議書を提出した伊豆韮山代官の江川太郎左衛門坦庵公に命じて、洋式の海上砲台を建設させた。品川沖に11基の台場を一定の間隔で築造する計画であった。工事は急ピッチで進められ、およそ8ヶ月の工期で1854年にペリーが2度目の来航をするまでに砲台の一部は完成し、品川台場(品海砲台)と呼ばれた。お台場という呼び方は、幕府に敬意を払って台場に御をつけ、御台場と称したことが由来である 。埋め立てに用いる土は高輪の八ツ山や御殿山を切り崩して調達した。 ペリー艦隊は品川沖まで来たが、この砲台のおかげで横浜まで引き返し、そこでペリーが上陸することになった。台場は石垣で囲まれた正方形や五角形の洋式砲台で、まず海上に第一台場から第三台場が完成、その後に第五台場と第六台場が完成した。第七台場は未完成、第八台場以降は未着手で終わった。第四台場は7割ほど完成していたが中止され、その後は造船所の敷地となる。また第四台場の代わりに品川の御殿山のふもとに御殿山下台場が建設され、結局、合計8つの台場が建設された[3]。 完成した台場の防衛は江戸湾の海防を担当していた譜代大名の川越藩(第一台場)、会津藩(第二台場)、忍藩(第三台場)の3藩が担った。 この砲台は十字砲火に対応しており、敵船を正面から砲撃するだけではなく、側面からも攻撃を加えることで敵船の損傷を激しくすることを狙ったものである。2度目の黒船来襲に対し、幕府はこの品川台場建設を急がせ、佐賀藩で作らせた洋式砲を据えたが、結局この砲台は一度も火を噴くことなく開国することとなった。 |
|
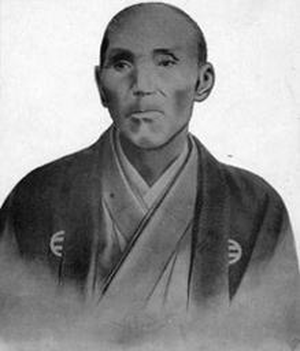 |
【大場の久八】 幕末維新期の伊豆の侠客。本名森久治郎。東海一の親分として勢力は駿豆相武の国におよび,現役中は清水次郎長も頭が上がらなかったといわれる。 嘉永6(1853)年黒船来航に際して江川太郎左衛門が品川沖にお台場を造営したとき,数千人の人夫を指揮して功績があった。 江川は江戸の屋敷に久八を招き,労に報いるため韮山代官支配地の御用を命じようとしたが,「骨が舎利になっても二足の草鞋ははかぬ。渡世人は堅気の下につく者だ」と断ったという。 維新後は博徒の足を洗って帰農し,下田街道の改修や村の小学校建設に貢献した。 6尺2寸の大男で右目が斜視。強力(ごうりき)で健脚の持ち主とされ三島と江戸を1日で往復して平気な顔をして畑仕事をしていたという。 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
農兵節と三島女郎衆
