農兵節と三島女郎衆
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| 江戸時代の三島女郎衆の生計の場は小さな木造二階の飯盛旅籠(めしもりはたご)、旅籠はそれぞれ独立し十数軒営み続けていたが明治中期に至って「花本」「宝来」「中川」「尾張」「稲妻」「千歳」「井桁」「万字(後に万寿と改称)」「鳴海」「清水」の10軒に収斂している。 1919年(大正8)年には、野戦重砲兵第二連隊が、翌1920年(大正9)年には第三連隊が三島に配備され、約3,000人の兵隊が駐留し、兵隊相手の商売(遊郭、茶屋、写真館、遊技場、みやげ物屋など)が隆盛した。 しかしながら町の風紀上の問題も高まり、新しい移転先の土地買収や遊郭建築費などに多額の資金を必要としたため、5軒の業者はやむなく廃業することとなり、最終的には「稲妻」「尾張」「万寿」「井桁」「新喜」の5軒で遊郭を共同経営することになり、1925年(大正14)年に茅町(旧新地・現清住町)へ遊郭が移転し、戦後の売春防止法制定1956年(昭和31年)まで三島遊郭として存在しました。 清住町の建物は賃貸アパートとして昭和40年半ばごろまで残っていました。同遊郭は老朽化したとは言え、玄関が立派で木造2階建ての異様な建物だったと記憶しています。 大正時代以降にに造られた遊郭の2〜3階の違いはあれ基本的な遊郭の構造は下記の写真の通り全国余り変わらないと思います。 |
|
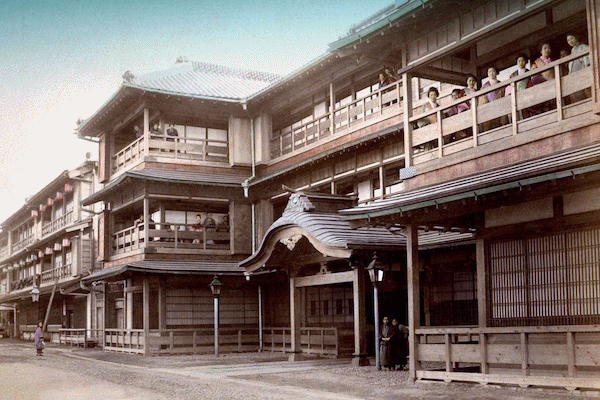 |
|
 |
三島の遊郭は、秀吉の命によりメインストー リトに堂々と建造されたが江戸時代に入ると 禁止令だけは町衆の強い上告により免れた ものの、次第に支道への移転を余儀なくされ 明治時代に入ってからは、主要街道から目 の届きにくい場所へ移転している。 例えば、三島宿では現在の広小路駅から南 西約1km離れた新地(旧茅町)現在の清住町 に遊郭が建てられ、赤線廃止令後も建物は アパートとして昭和40年代まで存在していた のを確認している。 江戸時代にはもっと小さな旅籠だったと思う が、大きな木造校舎に豪華な玄関屋根があ る一般庶民にとっては異次元の世界であっ たに違いない。 |
 |
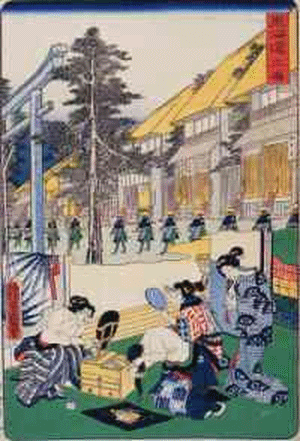 |
 |
|
| 江戸時代末期、常連客の大半が村の名主や韮山塾の塾生などで、旅人より近郊近在の人々に有り難がられていたらしい。お代500文、旅籠の取り締まりは、小田原ほどには徹底していなかったようだ。寺院の境内地には、月ぎめの私娼までいたという。 本来取り締まるべく立場の韮山代官ひざ元の塾生が三島女郎衆に通っていたということは、代官の寛大な人柄が偲ばれ、農兵の行進曲に大胆に使用したということは、江戸幕府のご法度を革新的に無視していたということか?そんな気がしている。 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
農兵節と三島女郎衆
